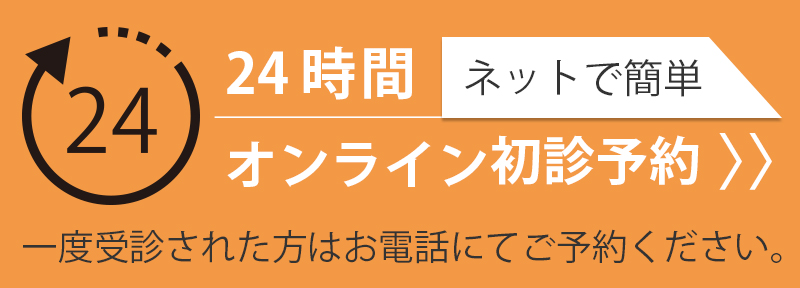治療後に歯がしみて痛い理由は?
こんにちは。福山市 医療法人幸美会 なかむら歯科クリニック トリートメントコーディネーター 沖村です。
突然ですが皆さん、今まで歯医者さんに行って、冷たいものにしみていなかった歯を「ここに虫歯があります。歯を削って治療していきますね」と説明を受けた後、治療を受け、自宅に帰った後、飲食すると、急に冷たいものがしみて歯がズキズキ痛いという経験はありませんか?

これには理由があります。
そもそも虫歯の治療を行う際には、虫歯の部分を全て取り除いて行うことが大前提です。
虫歯を残して処置することは、錆びついた看板に錆を取り除かず、ペンキを塗ることと同じです。
そのため、ペンキ塗り状態が優れない事と同様に、虫歯を全て取り除かないと修復処置は出来ないのです。
その為に、虫歯の治療時には虫歯を全て取り除きます。深い虫歯がある場合には、虫歯除去中に神経に対してどうしても刺激が伝わる事となります。これにより、処置前の疼痛の有無に関わらず、神経が生きている歯は虫歯処置後に冷たいものにしみたり、痛みが出る場合があります。
個人差はありますが、通常はしばらくしたらしみる事や痛みは軽減してきます。しかし、軽減することなく痛みが増してくる場合はやむを得ず、神経処置を行う場合があります。
虫歯が深い場合、神経処置をやむを得ずに最初から行う場合もありますが、できる事なら神経処置は極力行わない方が、歯の寿命を考えるといいと言われています。
樹木でも根を刈ると水分が失われ、急に寿命が減ることになります。歯も同様神経処置を行うと、歯の寿命が短くなるという結果を招きます。
この観点から、当院では処置後の疼痛の可能性を患者様に説明し同意を得た後に、神経がある歯の虫歯処置には、極力神経保存療法を試みています。
治療後に歯がしみる事がありましたら1度歯医者に行ってみてください。

福山市 医療法人幸美会 なかむら歯科クリニック トリートメントコーディネーター 沖村
歯並びを気にされている方へ
こんにちは。福山市 医療法人幸美会 なかむら歯科クリニック 歯科衛生士の富田です。
皆さんは、ご自身の歯並びを気にされたことはございませんか?歯並びが悪いと、見た目が一番気になると思いますが、歯並びが悪い事で様々な障害があるんです!
今回はそういった、歯並びが悪い事で何が生じるかを紹介していきます。
まずは、不正咬合の種類について紹介していきます。
【反対咬合】 嚙み合わせた時に、下の前歯が上の前歯よりも、前に出ている状態。
【上顎前突】 一見綺麗な歯並びに見えるのですが、上下ともに前歯が前方へ突出しており、口元が前へ突き出ている状態。
【叢生】 歯の生えるスペースが不足しているために、歯並びが乱れ、歯がデコボコになっている状態。
【上顎前突】 『出っ歯』と呼ばれるもので横から見た時に、上の前歯が下の前歯に比べて、極端に前に出ている状態。
【開口】 上下の前歯が噛み合わずに前方へ開いている状態。前歯が開くだけではなく、唇まで常に開いた状態になることもある。
【過蓋咬合】 上の歯の咬み合わせが深くなった状態。
では、この不正咬合を放置するとどうなるのでしょうか?
・見た目の劣等感
・咬むという機能不全
・咬み合わせのバランスが悪く、顎関節の症状が出る
・虫歯、歯周病のリスクが将来的に高くなる可能性
・歯磨きがしにくい
・咀嚼機能低下による胃腸への負担が増える
そこで、この不正咬合を矯正して治療を行うメリットについて紹介していきます。
《矯正治療を行うメリット》
・歯列の改善により、口腔機能の改善(発音、顎の発育、咀嚼、咬合など)
・歯磨きがしやすくなる
・虫歯や歯周病リスクの軽減
・食事の際、しっかりと噛む事ができる
・顎関節症や肩こりなどの解消にもつながり、身体全体のバランスが整う
・審美的改善、見た目のコンプレックスが解消され、口元を好印象に
皆さんも歯並びが気になる際は、気軽に声をかけてくださいね。
福山市 医療法人幸美会 なかむら歯科クリニック 歯科衛生士 富田